【モンテッソーリ公開復習会レポート】 第1回 <モンテッソーリ教育って、どんな教育なの?>
開催背景と今回の復習テーマ
私たちは、AMI(国際モンテッソーリ協会)公認のモンテッソーリ教師として、時折「Montessori Nature」というイベントを開催して、自然の中で子どもたちが感覚を通じて活動しながらモンテッソーリの活動やエッセンスを体験してもらう時間を提供してきましたが、このたび、そのイベント名である「Montessori Nature」が商標登録されました。
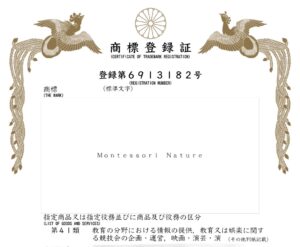
それをきっかけに、もっとこういった時間を増やしていけたら良いなという想いとともに、モンテッソーリ教育を学んだ時の資料を見返していたら、
「これはすごい!」と改めて感動したり、
少し忘れかけていた内容もあったり(汗)、
今の自分たちの視点から見える新しいこともあったり…
様々なことを思う中で、学びの復習をしようという話になりました。
私たちの願いは、子どもとの関わりによって、子どもももちろん、大人も楽しく過ごせたらいいなということ。
この復習会を公開にしてみたら、もしかしたら楽しんでくれる誰かがいるかもしれないという思いから、この企画をはじめることにしました。
【第1回 モンテッソーリ公開復習会テーマ】
<モンテッソーリ教育って、どんな教育なの?>
〜ここがおもしろい&本質的!と思っているモンテッソーリ教育の根底にある考え方。モンテッソーリ教育は乳幼児からシニアまで〜
復習トークサマリ
―モンテッソーリ教育とは?
恵子: 第1回目は<モンテッソーリ教育って、どんな教育なの?>、〜面白い&本質的!と思っているモンテッソーリ教育の根底にある考え方。モンテッソーリ教育は乳幼児からシニアまで〜というサブタイトルをつけています。
この後、毎月色々なテーマで話していくのですが、「モンテッソーリ教育とはどんな教育なのだろうか」という大前提のところやっておくと次回以降の各論に繋がっていくなと思ったので、初回はこのようなテーマを持ってきました。
祐介: 少し、自分たちもそこの理解をさらに深めたい、みたいなところもあるので、そこから行きましょう。AMI(国際モンテッソーリ協会)の教師トレーニングセンターのホームページではこのように書かれています。
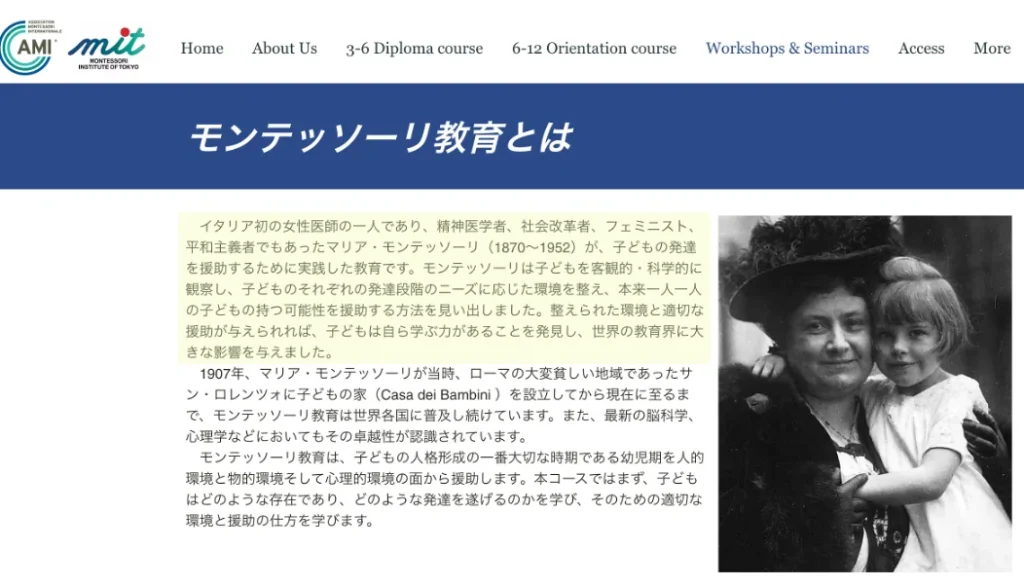
東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター HPより
祐介: いくつかここでのポイントをお話すると、モンテッソーリさんが女性医師だったというのは、かなり大きな特徴ではあるかなというように思っていて、子どもを客観的、科学的に観察したことによる教育だ、ということです。そして、発達段階のニーズ、一人ひとりの子どもが持つ可能性を援助する方法がある、ということを観察から見出していったんですね。
それから、整えられた環境と適切な援助が大事であり、それをすることで、要は「大人から教えこまれなくても、子どもって自分から学ぶ力があるのだ」ということを発見したということが、ざっくりと書いてあります。
恵子: そうだよね、「自己教育力」ってワードでよく言われるよね。
祐介: その通りなのですが、今日のタイトルにもある通り、モンテッソーリ教育の考え方は、例えば高齢者向けのモンテッソーリケアのような領域で、高齢者の方とか認知症の方向けのサポートとしても使われたり、モンテッソーリスポーツのようなものがあったりします。
モンテッソーリ自体は幼児教育のイメージが強いですが、 海外に行くと、小学校、中学校、高校とかであったりしますし、かなり実は人類の全領域に関わっている、というようなところがあります。
そこの大前提のようなところを、何か話せると良いかなと思っていて。少し具体的なHowの話にはなりづらいのですが、でもすごく大事なポイントに思いますので、今日はそのような時間にしたいなと。
―世界の教育の歴史
祐介: では、まず少しだけ社会、世界の教育の歴史のようなところを、さっと話しながら、それとモンテッソーリ教育の関わりのようなことを話せると良いかなと思っていて。
大きく言うと、歴史上、教育というのは宗教教育のようなところから始まっていて、中心には神様がいて、そして神様の教えをどう伝えるかというようなところが教育の根底にありました。それは教会がすごく大事で、だから聖職者の人がそれを学ぶ、というような感じから始まったのですが、その次に神中心の教育から、人権という概念とか人間が大事だよねという概念が出てきて。
恵子: 人にスポットが当たってきたんだね。
祐介: 人間を中心とした教育のようなものが、社会のニーズによって出てきました。人で言うとルソーとかそういう時代で、ルネサンスとか、フランス革命とか、そういったものに繋がっていくような教育ですね。昔は神が人を作っていて、人の地位がかなり低かったのですが、その人間教育の時は「人間が人間で自分たちの社会を良くしていけるよね」みたいな発想が出てきている時です。
そこからさらに時代が進み、今度は産業革命とかが起こってくることによって、「あ、皆が同じことができる必要があるな」となる。
恵子: 国が大きくなったから、ということね。
祐介: そうそう。国が大きくなってというのが出てきて、それで公教育のようなものが出てくるわけ、ざっくり言うと。
もっと細かくはあるけれど、さらに時代が移り変わり、皆で一斉にやることが良い社会を作る、という時代から、何が答えか分からなくなってきたとか、色々な答えがあるよねとか、色々な方向性が社会にとって大事だよね…ということなどが起こってきた中で、一斉教育ではなくて、その人その人に合った教育が大事だよね、というような文脈の中で、モンテッソーリ教育が語られることが多いように思います。
その人の発達に合わせた教育とか、その人の個性とか個体差のようなことが大事にされる教育ですから、そのようなことが、モンテッソーリもそうですし、他の、例えばイエナプランとか、そのようなところもそうだと思います。
モンテッソーリ教育というのはその時代に、ニーズに合った教育だ、とすごく広がっていっているというのはあるのですが、そのような歴史的背景も多分にありつつも…
私がここで言いたいのは、先ほど観察のような話がありましたが、モンテッソーリさんは、時代のニーズに応えたかったわけでは、おそらくなくて。医師の勉強とか仕事を通して、人というものを観察していたのですよね。そして観察していたら、「あれ? 人間ってこういう生き物なのではないだろうか?」みたいなことが発見されてきて。
恵子: うん。
祐介: 人間という生物はこういう特徴を持っているよね、というのを発見して「こういう生物だったら、こういう関わり方が良いのではないか?」ということを形にしたのがモンテッソーリ教育という理解です。なので、そこが実はすごく面白いなと思っています。
普通の教育というのは社会背景があり、その中で要請された教育が出てくるのですが、人間観察から始まっている、というのが面白い。そこが本質的だと思いますし、人間観察から始まっているから、時代に左右されづらい。そんなふうに思っていたりします。
恵子: さっき話してくれた歴史の、神の教えを引き継ぎたいとか、人が大事だとか、皆が同じことができることが大事とかを起点に、「だからこういう教えを作って人に渡そう」ということではなくて、人を見て、「人間というのはこういう生き物なのだ。だからこういう関わりをすると良いのではないか」というように導き出した、というのが特徴でもあるし、人を起点にしているから、時代に左右されず、社会にも左右されず、存在しているというか、そこが本質的ということだよね。
祐介: そう、そこが自分が面白いなと気に入っているところです。
恵子: さっき見たホームページにも、観察して導き出した方法ですよみたいなことが書いてあったもんね。
―モンテッソーリが観察によって導きだしたもの
祐介: そして、その観察して導き出したものを、モンテッソーリの言葉で言うと「人間の傾向性」という言葉でまとめているのですよね。
恵子: いくつか導き出したものがあるけど、そのうちの一つに「人間の傾向性」というものがある、という感じかな。
祐介: その傾向性の、より具体に関しては次回話そうと思っているのですが、傾向性もモンテッソーリ教育を知る上ですごく重要なので、その大きなところ、「傾向性とはこういうものだよね」という話を今日少し話せると良いかなと。
「傾向」というのは、向かうとかそちらに傾く習性。
「傾向性」の定義は「人間が環境に適応し、潜在能力を発揮するために取る、特定の行動へ向かわせる内なる力」。これはどういうことですか?
恵子: 下に書いてある引用なども合わせて読むと良いのかもしれないね、「内側から駆り立てる強い力で、人がより人間らしくなるために、私たちを後押ししてくれる衝動のようなもの」。
祐介: その人がその人になっていくために、内側から出てきてしまう衝動。これが人間という生物の特徴なのだ、というのを見つけたんですよね。
恵子: そして、定義のところに「人間が環境に適応し」というように書いてあるんだけど、モンテッソーリ教育はこの「適応する」というのも大事にしているよね。適応するということ自体は、モンテッソーリ教育では何というかすごく幸せなことだと考えていて。
平たく言うと、「自分はここにいて、ここの場所に受け入れられていて幸せだ」とか「ここは自分がいるべき場所だし、この場に役に立てている」というのを感じられる満足感のようなものとか、そういうことに繋がっていくので、適応するということはすごく、まず前提として大事です。そして、幸せなことだと考えています。
祐介: そうだよね。その考え方が根本にありますよね。自分で自分というものを作りながら適応していくし、それはすごく幸せなことなのだとか、その環境をより良くしていきたい、というようなことも含めて、適応していくというのが大事とされていますよね、という感じです。
あと、モンテッソーリさんの考え方の根本でいくと、生物としての人間、というようなこととか、生物として環境に適応していくとはどういうことか、みたいな話もあるなと思っていて。
恵子: さっきと同じ箇所で「人間が環境に適応し」と書いてあるのですが、そもそも人間であっても他の動物であっても、生き物は自分の置かれている、暮らしている環境に適応していくということは、そもそも必要なんだよね。なぜなら、適応しないと生きていけないから。
祐介: 生きるためにね。
恵子: そう、生きるために全ての生物が適応する必要がある。
その上で、人間と人間以外の動物を比べて見てみた時に、動物は実は生まれた瞬間から、かなり適応できたりする。生まれた瞬間に自分の足で立てるとか、獲物や餌の取り方を知っている、あとはその生まれた場所にあった体つきをしてるとか。
祐介: 北極熊であれば、毛皮があって、北極で過ごせるために適応してる状態で生まれてくるみたいなね。
恵子: という感じで生まれてくるので、生まれた瞬間からその環境に適応することができるんだけど、人間は丸裸で、立てない、自分の手で飲んだり食べたりできない、喋れないからコミュニケーションも取れない、というような状態で、適応するという観点では、かなり遠い状態で人間は生まれてくる。すごく未熟な状態で人間は生まれてくるのですが、
祐介: 初めはね。
恵子: そう、初めはね。なのですが、どんどんその環境に適応していかなければいけない。
祐介: うん。というか、私の理解だと、初めは、生まれた瞬間適応しているのが人間以外の動物で、生まれた瞬間は適応していないけどその後に適応していく、というものを強く持っているのが人間の特徴。まあ、おそらく同じことを言っていると思うんだけど。
その適応するために発揮していく力が「人間の傾向性」かなと。だから、それを発揮するということによって、適応に繋がっていくということなのだなと思ったりします。
それで、なぜそうなっているか、というような話でいくと、これはおそらく生物の進化の歴史なのですよね。動物はもう適応した状態で生まれてくるのですが、逆に言うとそこ以外の場所には住めない、という話が出てくるわけです。北極に生まれた北極グマが、暑い砂漠には住めない。
人間というのは初めは適応できていないけれど、どこにでも適応できるという特徴があるので、それでいくと人は世界中どこにでもいますよね。寒い地域にも、暑い地域にも適応していくということが、人間の特徴なのだし、それが動物と人間の違いという感じかなというように思います。
それで、その傾向性の特徴のようなところにより入っていくと、「阻害されない限り作動する、内面から湧き起こってくる力」というのがあって。
恵子: さっきの、内側から駆り立てる強い力とか衝動というところだよね。
祐介: そして二つ目。「発揮することで満足する。自己構築をする。自己実現をする」。
恵子: これはそうだね。だって衝動として起こっているのに阻害されたらストレスだし、発揮できたら満足するよね。そして自己構築、自分を作っていく。
祐介: 人がより人間らしくなるための衝動だから、することによって満足するし、発揮することでその人がその人になっていくということだよね、と。
三つ目は「人間の生涯を通じて機能するもので、居住地域、文化、宗教、人種、経済状況、風習などに関わらず、全ての人間が持っている」ということ。南米の人も持っていれば、日本の人も持っていれば、北欧の人も持っている、みたいな。子どもも持っていれば、大人も持っていて。人間の生涯を通じて機能するというものなのですよね、と。だから、初めの話に戻ると、幼児だけではなくて、高齢者の方とか、小学校、中学校、高校とかですね。大人まで、というようになっています。
そして次の「動物が持っている本能とは違う」というところでいくと、要は生まれながらに適応しているか、少し言葉が正確か分かりませんが、後から適応していくかの違い、というような話だと思っています。
―観察で見出した人間の傾向性とは、例えばどんなこと?
祐介: で、モンテッソーリさんが見出した人間の傾向性、というようなものが14個ぐらいあります。
人というのはどこに行っても「探索」する生き物ですよねとか、「位置確認」というのをするという特徴がありますよねとか、「秩序」とか「観察」とか色々ありつつ。
例えば、そうですね、一つぐらい取り上げておくと「手を使う活動とか仕事」というのは、人間という生物の傾向性であり特徴です。
生物的にも、二足歩行で手を使うというのは人間の特徴だと思うんだけど、ここに書いてあるのは「手を使って活動して環境を良くしたい」とか、「手を道具として目的を成し遂げたい」とか、「手は脳の道具として機能する」みたいなことが書いてありますね。
だから、その環境に適応していくとか自分を作っていくというのは、手を使いながら、自分、例えば自分自身が好ましいと思う環境を作っていく、というようなことも言えると思いますし、それによって環境に適応していくとか、道具を作って ー昔で言えばそれで火を起こすとか狩りをするということによってー 自分をその環境で生きられる自分に適応させていくとか。より居心地の良い、自分が満足する環境に作っていくとか、そういうこととも言えるかなというように思います。
恵子: これ、子どももよくあるよね。手を使って何かしたい、という欲求が見られるな、と思う時。
祐介: うんうん、例えば?
恵子: 例えば、家庭で日常生活の中でよくあるなと思うのは、私が夕飯を作っていてキッチンに立っていると「一緒にやりたい」と言って、自分で手を使って野菜を切るとか、鍋の中で調理するというようなことやったり、掃除していると「やりたい」と言って、一緒に動き始めることとか。
あと最近、朝子どもの方が先に支度ができていて、私の支度が終わらなくて待っていてくれている間、玄関をほうきで掃いていたり。玄関を掃くというのはまさに環境を良くしたいということに通じるのかもしれないけど、何か手を使って活動したいというシーンはよくあるなと思ったりする。
祐介: うん。それは、モンテッソーリ的に言うと、人間の傾向性を発揮しているということかもしれないですね。阻害もしていないしね。
恵子: そう、阻害もしていない。時には大人側に時間の余裕がなくて「料理手伝ってほしい気持ちもあるのだけれど、ごめん!今はちょっと難しい!」みたいな時もあるんだけど。
祐介: そう、阻害しない限りは傾向性を発揮できている、そして発揮できると、先ほど書いてあったように満足する。
モンテッソーリ教育に置き換えると、かなり手を使った活動がたくさん用意されていたりします。それで、よく「何か細かいことをやっていますよね」みたいに言われたりしますが、それは手を使いたいという人間の傾向性を発揮できるように環境を作って整えている、そういう意味合いなのですよね。
恵子: そう、発揮できるように環境を用意している。
祐介: あとは、その先ほどの高齢者の話で、認知症ケアでも例えるならば、例えばデイケアとかをイメージしていただいた時に、そういう環境がないとやはり活動ができないので、少し寝たきり気味になってしまうとかそういうことがあり得るかもしれない。
観察をして「あ、今、手を動かしたいという人間の傾向性が出てるな」、「じゃあその人がどういうことが好きなんだろう」とかを見出せると、例えば「植物を育てるのが好きだから」みたいなことがあった時に、手を使って植物を育てる活動を用意してみたり、結果すごく楽しそうに取り組める、そしてそれはより良い環境を作り適応することでもあり満足する、みたいなことが現れてくる。
というのは、人間の傾向性が現れているからそうなるのだ、そういうように捉えられるのかな、というように思いました。今日は手を使う、というのを少し取り上げて話してみましたが他にもたくさんあるので、そこはぜひ次回話ができると良いかなと思っています。
そんな感じですかね。なので、モンテッソーリ教育とは何か、というようなところを一旦まとめるとするならば、どうですか?
恵子: そうだね。冒頭の歴史のところあたりで話したかな、という気がするけどやはり特徴の一つは「観察」をベースにしている、ということかなと思っていて。社会とか時代とかの流れによって生まれたものというよりは、人間を観察して、「人間とはこういう生き物なのだ。だからこういう関わりとか援助が良いのである」というように生まれたというのが、ある意味、その時代とかにも左右されない普遍的な教育である、というところが、やはり特徴かな、ということと。
あとモンテッソーリ教育は日本では幼児期のイメージが強いけど、人間を観察しているというところからスタートしているので、幼児期に限定されなくて、実は私たちぐらいの世代とか、もっと上の年代まで、応用が効くというか、展開できるというか。そういう教育なのだな、というようなところですかね。大きくまとめると。
祐介: そうですね。何か「人間とは何か」というようなことを、かなり追求している感じがしていて、そこがかなり好きですね。気に入っているポイントです。
恵子: 今日の第1回目のテーマは、このようなところで終わっていきたいなと思います。次は、先ほど少しお話しした傾向性とか、もう少し各論っぽい話に入っていけると良いかなと思います。

最後に
今回は、モンテッソーリ教育という名前は聞いたことあるけれど詳しくは知らないという方から、以前学んだことがあり改めて復習したいという方まで、さまざまな方に参加いただきました。
そして上記の復習トークを聴いていただいた上で、ご参加のみなさんから気になることやご質問も出していただいて、復習会の後半ではそのことについて私たちもご参加の方も含めて対話させていただく時間となりました。
みなさんの観点や実際の体験を通したご意見・ご質問を通じて、私たちも改めて見直したり、考えたり、気づいたりする機会になりました。
復習会をご一緒してくださったみなさま、ありがとうございました!
公開復習会は今後も毎月テーマを変えて継続する予定です。
平日のランチタイムに開催していますので、ご興味のある方は、ぜひお気軽にご参加ください。
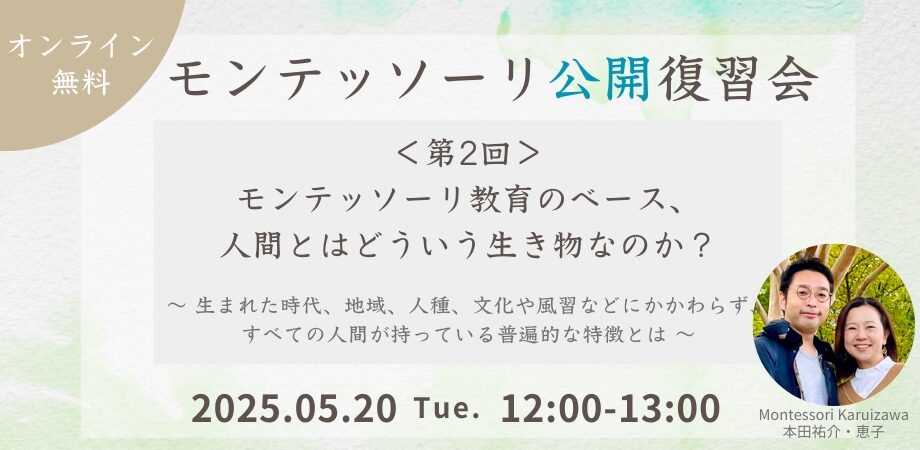
【第2回モンテッソーリ公開復習回 開催概要】
テーマ:
<人間とはどういう生き物なのか?>
〜 生まれた時代、地域、人種、文化や風習などにかかわらず、すべての人間が持っている普遍的な特徴とは 〜
──
日時:2025年5月20日(火)12:00-13:00
──
場所:オンライン開催
※お申し込みの方には別途ZoomURLをご案内いたします
──
参加費:無料
──
お申し込み方法:
Peatixよりお申し込みください


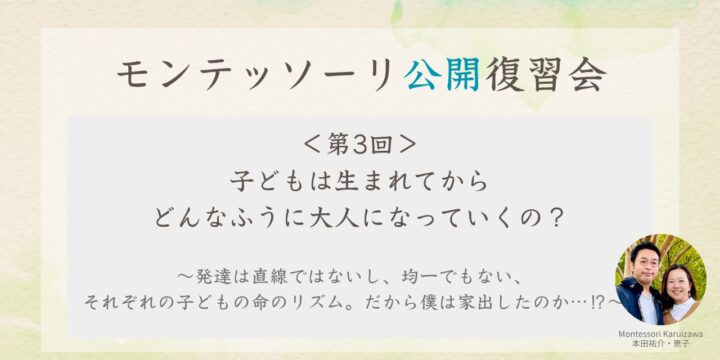

この記事へのコメントはありません。