【モンテッソーリ公開復習会レポート】 第2回 <モンテッソーリ教育のベース。人間とはどういう生き物なのか?>
今回の復習テーマ
AMI(国際モンテッソーリ協会)公認のモンテッソーリ教師である私たちが、時折開催している「Montessori Nature」というイベントの名前が商標登録され、それを機に改めてモンテッソーリ教育について学び直し、復習する時間を持つことに。
私たちの願いは、子どもとの関わりによって、子どもももちろん、大人も楽しく過ごせたらいいなということ。
この復習会を2人の中に閉じず公開したら、一緒に楽しんでくれる誰かがいるかもしれないという思いで、先月からこの企画をスタートしました。
そして第2回目の復習会のテーマはこちら。
【第2回 モンテッソーリ公開復習会テーマ】
<モンテッソーリ教育のベース。人間とはどういう生き物なのか?>
〜生まれた時代、地域、人種、文化や風習などにかかわらず、すべての人間が持っている普遍的な特徴とは〜
復習トークサマリ
―モンテッソーリが観察によって見出した「人間の傾向性」
祐介: 今回は人間の傾向性というところに入っていくけど、まずどう定義されているかでいくと
「人間が環境に適応し、潜在能力を発揮するために取る特定の行動へと向かわせる内なる力。」
と言われていて、環境に適応するというところが結構ポイントなのかなと。
人間って環境に適応していく生き物だということなんだけど、環境って色々ある。寒いところで生まれれば、寒いところに適応しようとするし、暑いところに生まれたら、暑いところに適応していこうとする。あと生まれた社会も環境。社会とか、カルチャーにも適応していこうとする動物なんだということです。
恵子: 日本に生まれたら、日本のカルチャーに自然に適応していくというね。
祐介: そう。そして環境に適応していくことで、「ああ、自分はここにいていいんだな」と思えたり、環境に適応していく過程で内なる力を発揮することによって、その人がその人らしくなっていく。
環境との相互関係の中で、その人がその人らしくなっていくということが起こるよねということが言われています。
もう少し特徴を話すと、一つは、阻害されない限り作動する、内面から湧き上がってくる力ということ。
そしてそれを発揮していくと、自分で自分を作っていく、その人がその人になっていく、それって自己構築に繋がっていくよね、と。
あと、傾向性は生涯を通じて発揮していくから、子どもだけではなく大人も、おじいちゃんおばあちゃんも、人生を通じて発揮していく。だからモンテッソーリ教育って子どもだけじゃないんだ、という話も前回しました。
それから居住地域、文化、宗教、人種、経済状況、風習などに関わらず、全ての人間が持っているということ。 もちろん自分のいる居住地域に適応しようと環境に合わせて発揮されるけど、どこに生まれようが人間は持っているんだという話。
もう一つは、動物でいう本能とは違うと言われていて、ここがどう違うのか、というのが結構説明が難しいのですが…
―本能との違い
祐介: 本能って結構固定化されているんですよね。 亀が生まれると海に向かっていくとか、鳥は必ず巣を作るとか。それらは動物の本能みたいなものだけど、固定化されているんです。
人間の傾向性は何が違うかというと、先ほど言ったように、暑い地域では暑い地域に適応しながら、その環境に合わせて発揮されていくものなんだよね。
恵子: なるほどね。
祐介: 環境と相互作用の中で発揮されていて、柔軟性がすごくある。 あるいは、逆に環境にすごく左右されるとも言えるんじゃないかなと。そして、そこが動物の本能とは少し違うのかな、と思います。
固定化された反応ではないし、社会の影響も受けるから、その社会の文化との相互関係の中で発揮しながら、自分自身を作っていく、そういうことが起こるということかなと思っています。
祐介: そして、モンテッソーリさんがもう一つ言っているのは、本能は種の生存とか繁殖を目的にしているけれども、 人間の傾向性は適応しながら自分自身を作っていくという、自己実現みたいなことが人間の特性としてあるんだ、と。
あと、環境と適応しながらいくから、それが繰り返され積み重なっていくことで、ひいては、文化の創造とか文化を継承していくようなところも人間の特徴としてあるよね、ということが言われていたりします。
ここまで聞いてどう?
恵子: なんか環境との相互関係の中で傾向性を発揮しながら適用していくって話でいくと、もちろん社会もあるけど、一番小さな単位で言うと家庭にも適応していこうとするわけじゃない?その家庭ならではのやり方とかそういうものにも子どもが適応しようとするわけだから。何て言うか、環境ってすごい大事だな、と思った。
祐介: そうだよね。だからモンテッソーリ教育もすごく大事なところって、その傾向性とかが発揮されるような環境を用意するのが大人の役割だよね、みたいなところもあるし。 子どもが自分で自分を作っていくことができるようにする、そういうニュアンスがあるなという風に思います。
ここからは、実際人間の傾向性ってどういうことがあるの?という話をしていけるといいかな。

―具体的な傾向性の例
恵子: 具体的に入っていく前に、ちょうどこのページの下に「決まっているリストではない」と書いてあるんだけど。
リストではないので、必ず「これとこれとこれがあります」ということではないし、その傾向性が同時多発的だったり関係し合いながら、総合的に人間の傾向としてあるんだな、みたいな感じで捉えてもらえるといいかな、と思います。
祐介: うん。混ざり合ってたりとかね。発揮されてるタイミングされてないタイミングがあったりみたいな感じですね。
探索|位置確認|秩序|観察
恵子: ちょうどグループに分けて書いてあるので、グループごとに見ていくと、このグループには「探索」「位置確認」「秩序」「観察」こんな傾向性が書かれています。
祐介: どこの地域に住んでても、どんな文化を持っていても、全ての人が持っている人間の行動の特徴としてこういうことがあるよ、みたいな。
恵子: 細かくは色々書いてあるんだけど例えば、みたいな話をすると。
最初に「探索」や「位置確認」があったけど、そして子どもだけじゃなないよという話もしたと思うんだけど。私たち大人も例えば引っ越して全然今まで知らなかった地域に家を構えたとか、日本とは全然違う、例えばパリとか海外に旅行に行った時って、その町のどこに何があるのかということを探索したくなったりするよね。
で、「あ、あそこにスーパーがあるんだな」とか「ここにこんなお店があるんだ」という位置を確認できると安心できるし、「ここを起点にまたその周りを探索してみよう」と安心して楽しめるようになるなと思って。そういうのはまさに「探索」や「位置確認」の傾向性を発揮しているシーンかも。
子どもで言うと、うちの子どもも小さいときそうだったけど、家の中のドアや引き出しをたくさん開けて、中に入っているものを色々出したりしながら何が入っているのか確かめるような行動も、「探索」や「位置確認」の傾向性の現れかもしれない。 そこでここに何があるということが分かると、もしかすると次の「秩序」にも繋がる気がするけど、空間のここにこういうものがある ー タオルとか服とか、おもちゃの場所とか ー というのが分かると、自分で行動しやすくなったりそういうことに繋がっていくし。
そして色々探索する中で、どうなっているのかをよく見る、観察することも子どもはあるなと思ってて。特に小さい時って親の口の動きをよく見ていて、声を出す時に「こういう口の形をするとこの音が出るんだ」みたいなのをすごく見ていたり。それも「観察」の傾向性なのかな、と思った。
祐介: そうだね。今言ってくれたことって、子どもを見てもよくしているし、我々もよくしているんだけど、これって人間の特徴なんだよね。
その場所に何があるかわかることはすごく安心だし、これが発揮されると安心に繋がるとかね、そういうことって確かにあったりするなと。
恵子: 今話しながら思ったのは、コロナの時って最初は結構家を出ちゃいけないみたいな感じで、閉じこもっていたじゃない?家の中ではできるかもしれないけど、外に探索しに行くことはできなくて、それってさっきの特徴のところにあった阻害されて発揮できなかったということだと思う。
あとは、災害とか停電とかがあって例えば道端の信号が消えちゃった!ってなると、信号の赤になると止まるというのは秩序だから、秩序がなくなって安心できなくてちょっと混乱したり不安になる、みたいなことがあるかなと。やっぱり傾向性が阻害されるとか、発揮できないことって、不安だったりストレスだったりそういう感じに繋がるな、と思ったりした。
祐介: まさにコロナはそうだよね。
スーパーでいつもある場所にあれがない、とかもね。それがストレスに感じるってことは、この傾向性がちょっと阻害されたというか、傾向性と違うことが起きたから、みたいな何かそういうことだよね。面白いね、人って。
じゃあ続いて、次のグループ。
手を使う活動・仕事|間違いの自己訂正・繰り返す|正確さを求める・精度を高める|自己コントロールする|自己完成に向かう
祐介: 環境に適用しながら自分で自分を作っていく、みたいなことをさっき人間の傾向性の特徴としてあったけど、何かそこにつながる傾向性が書いてある感じがするよね。
恵子: うん。そうだなあ…例えば、子どもが自分のイメージした電車を、ダンボールを使って切ったり貼ったりして作る活動をしていたとして。でもそこで出来上がったものが、イメージしたのとは違っていて納得がいかない、うまく出来上がらなかったみたいな時があったとする。そこでまたダンボールを持ってきて、「もうちょっとここをこんな形にしたらいいんじゃないか」「こことここを繋げてみたらいいんじゃないか」というようなことを自分なりにやり直して繰り返しながら、より精度の高いものを、繰り返し満足いくまで作るということがあるなと思って。
それってここに書かれている、実現したいことを自分の「手を使って活動する」。でも、それがちょっと気に入らないところがあった時に ー ここでは間違いという表現で書いてあるけど ー 「自分で訂正する」。何度も「繰り返し」てやり直して、自分のイメージに近い、「精度の高いものを作っていく」、そういう傾向性が現れているような時なのかな、と思う。
祐介: 何回も繰り返して、手を動かしながらやりたいって子どもだとよく表れるし、自分自身も結構そうで、前にオムライス作ったんだけど、うまくいかなかったから1日に何回もやって。
でも、やっぱり何回もやれる環境ってすごく大事なんじゃないかな、と思ったりする。 それちょっとまた後で少し話したいかもしれないな。
この「自己コントロール」というのも、自己コントロールするのが人間の特徴、内側から湧き上がってくる力なんだ、というのも面白いよね。
恵子: 誰かに「コントロールしなさい」と言われてやるものではなくて自分の内側から発揮したいものなんだ、というのは結構面白いよね。
祐介: 要は、自分で自分の思うように自分をコントロールしたい、ということなのかな。 モンテッソーリさんの本の中の例だと、昔人間が狩りをしていた頃、狩りをしようと動物を待ち構えていて、動物が現れた瞬間に「現れたぞ!」「来たぞ!」って騒いでしまうともちろん動物は逃げてしまうんだけど。そこを自分で「来た…!でも仕留められるまで待とう」って、自分を律してコントロールした結果仕留められるわけで。
そういう自分自身でコントロールすることによって、何かがうまくいくというのは、やはり人間の特徴なんだろうな。
恵子: あ、もう一個、「自己完成に向かう」というのがあった。でもさっきのオムライスの例みたいなのだよね。
祐介: そうそう。自分で納得するまでできると満足する、やはり繰り返せるって大事だよね、みたいな話。 自分の場合はもう3回作ったらそこから全く作ってないけど、自分の中で自己完成したし、自己満足したんだろうね。
コミュニケーション|社会性|抽象化|想像|精神性
恵子: 次のグループは「コミュニケーション」「社会性」「抽象化」「想像」「精神性」。ちょっとニュアンスが変わってくる感じだね。
祐介: あとは、この傾向性が出てくるのは、少し後から、と言えばいいのかな。
恵子: そうだね。幼児期というよりは、その終わりぐらいから児童期に入るぐらいに現れやすいのかな。
家族とか友達とか、人と人が一緒にいるとやはり誰かに何かを伝えたい、という気持ちになる。もちろん赤ちゃんの時も「あーあー」って、言葉にならない言葉で何かを伝えようとしてくれるんだけど、赤ちゃんの時ってまだ個でいるという感じ。そこからだんだん他の人と関係性を築き出して、社会性みたいなのが現れてくると、「誰かと一緒にいたいし、その人たちと仲良くやっていきたい。だから、何かをちゃんと伝えていきたい」という風になっていく。そこで「社会性」や「コミュニケーション」という傾向性を発揮したいし。
コミュニケーションは、最初は手振り身振りみたいなことで昔は伝えてたのかもしれないけど、これをうまく効率的に伝えようと思った時に、文字とか記号とかを生み出して、「抽象化」していくことも人間はやってきたんだよね。
祐介: 確かにこれ人間全員が持ってるなって気がするよね。何て言うか、社会性の中でしか生きられない動物という風にも言えるかな、と思ったりするし。
あとうちの子どもを見ていると、今6歳だけど少し前から「ああ、急になんか友達といるのが楽しくなってきてるな」みたいな感じになって。この辺りの傾向性も発揮されてきてるな、と感じるよね。
恵子: これもさっきのコロナの時の話だと、多分「コミュニケーション」とか「社会性」のような傾向性は結構阻害されていたと思っていて。家に籠もっている感じだったから。やはりこの傾向性がなかなか発揮できなかった、という環境や状況は人間にとっては結構きつかったのかな、と。
祐介: あと、この辺は多分発達の段階とも関わってくるかなと思うので、また次回詳しく話せるといいね。
恵子:他に「想像」と「精神性」もあるけど、この辺も今出てきた発達の段階にからめて言うと、目の前のものを実際に触って活動するという段階から、だんだん宇宙に行くとか空を飛ぶとか、地球はどういうものなんだろうかとか、そういうものをイメージしたり知りたがったりすることに人間の意欲が向かっていったりするのよね。
「精神性」は…なんだろう、例えば動物が死んでしまった時に、土に埋めて、手を合わせて祈る、みたいなことは自然に子どものころからやっていたりすると思うんだけど、ああいうのも内側から自然に現れてくる傾向性の一つなんだろうね。
祐介: そうだよね。その人知を超えた何かというか、人ができないものへの憧れとか、逆に畏怖とかって確かに人間は持っているな、という気がするし。 ここにある例でいうと、見送る時に「出ていったら無事に帰ってきてほしいな」って、自分はコントロールできないんだけど、何かそういうことを願うとか祈るのが一つの精神性だし、それは人が持ってるものだな、と思った。
恵子: 一つ一つを細かくはお伝えできなかったけど、人間はこういうことを傾向性、内側から湧き出てくる力として持っているんだということを大まかに知ってもらえる時間になっていたら嬉しいな、と思います。
ちょっとここピックアップしたいな、みたいなところある?
祐介: 最後のグループのところはまた次回で話せるといいな、と思ったのでやっぱり自分で自分を作っていくみたいなところかな。
環境と相互作用しながら自分で自分を作っていくというのは、モンテッソーリ教育の根幹の一つかな、という風に思っていて。やはり、「間違いの自己訂正とか繰り返す」というところは、人間にとってすごく大事なんじゃないか、と改めて思ったかな。
大人になって仕事をすると、生産性が求められたり、一個やったら次は違うものをやろうみたいなことが起きがちで、たっぷり自分で繰り返しながら良いものをやるという時間ないな、と思ったりするんだよね。やはり阻害されてるんじゃないかな、みたいな。傾向性がね。
恵子: 何かちょっと間違いも許されない感じもあるよね。間違えてやり直して精度を上げて行こうというより割と良いものをすぐ出してね、みたいな。
祐介: もちろんそれも経済的というか、大事だと思うんだけど、人間の傾向性という観点でいうと、たっぷり間違いながら、たっぷり自分で検証しながら、自分でできるところまで持っていくというのはすごく根源的だなという気がするし、大事なんだろうなと思うし。
なかなかそれをずっと見守っているというのは難しいなとも思うんだけどね。
恵子: 今、見守るみたいな話も出てきたけど、さっきページの後ろの方にあった、この傾向性を知っておくとというところにも少し触れられるといいかな。
傾向性を14個全部覚える必要があるかというと、そうではないんだけど、こういう傾向性が人間にあるんだ、そういう生き物なんだ、ということを知っておくと何に繋がるか、という話。
例えば、目の前の子どもが傾向性を発揮しているのか、していないのかという観点で見られたとしたら。
傾向性って内側から湧き出てしまう、本来出したいものだし、発揮して環境に適用していきたい、というのがあるわけだから。 発揮できるように、自分も含めて周囲の環境を整えるということが私たちの関わりとしてできたりとか。
あとさっき「間違いを訂正して繰り返す」というのがあったけど、それができるような時間を取ってみる。
それをやるためには、その傾向性が出ているのか出ていないのか。 本当は出したいんだけど、阻害されているんじゃないか、とか。そういうことを観察することに意識を向けるということ。
そこに気づけると、大人の関わりや対応に活かせる。「今これをやりたい、発揮したいのかもしれないのに出せてないな」と観察で気づけた時に、私たちの声かけの仕方や関わりを見直したり修正したりできる。
そういう意味で、人間ってこういう傾向性があるんだ、というのを知っていることが大事なのかな、と思います。
祐介: そうだね。傾向性が発揮されるようなことを援助するというか、環境を整えるってやっぱり大事だ、というのを学んできたよね。
知っておくとやはり見方が変わるしね。この観察の例にも書いてあるけど、あちこち動き回ってることって、「落ち着きがないな」じゃなくて「探索したくてしょうがないんだな」と捉えられると全然違う。
恵子: 皆さんもあったかもしれないけど、子どもが赤ちゃんの頃にティッシュペーパーの箱からずっとティッシュを出していたことがあって…大人としては「もう止めてくれ〜!」という気持ちになるんだけど。あれも、例えば手を使うという傾向性なのかもとか、手でこういう風に引っ張ると何が起きるんだろうか、と探索の傾向性を発揮しているのかもしれないと捉えられると、その行動の受け止め方も変わるし、「やめなさい」というアプローチではないアプローチができたりもするなと思う。
モンテッソーリ教育は具体的なやり方やHOWに視点が行きがちだけど、そのベースとなっているのは、人間という生き物ってこういうことなんだ、ということ。 今日は、モンテッソーリさんが観察から見出した特徴の一つである、人間の傾向性というものについて復習する会でした。
今回は人間のベースとなる特徴を話したので、次は具体的に人間ってどんな段階を追って発達していくのか、というところに入っていきたいなと思っています。
最後に
今回も、私たちの復習トークを聴いていただいたあと、ご参加のみなさんからのご意見・ご感想をいただきながら話していく時間が楽しかったです!
復習しながらお伝えした内容が、子どもだけではなく大人にも通じる普遍的な考え方であることから、自分自身の幸せにもつながったり、パートナーの理解にも役立ちそう、などの声もあったのが印象的でした。
モンテッソーリ教育の考え方は、子どもに向き合う上で役立つのはもちろんのこと、大人である私たちの幸せのためにも応用できる考え方だと私たちも改めて思えた時間でした。
復習会をご一緒してくださったみなさま、ありがとうございました。
モンテッソーリ教育の考え方を身近に感じていただけたり、みなさんの関心に沿う内容があったら嬉しいです。
また来月もみなさんと一緒に学べる時間を楽しみにしています。
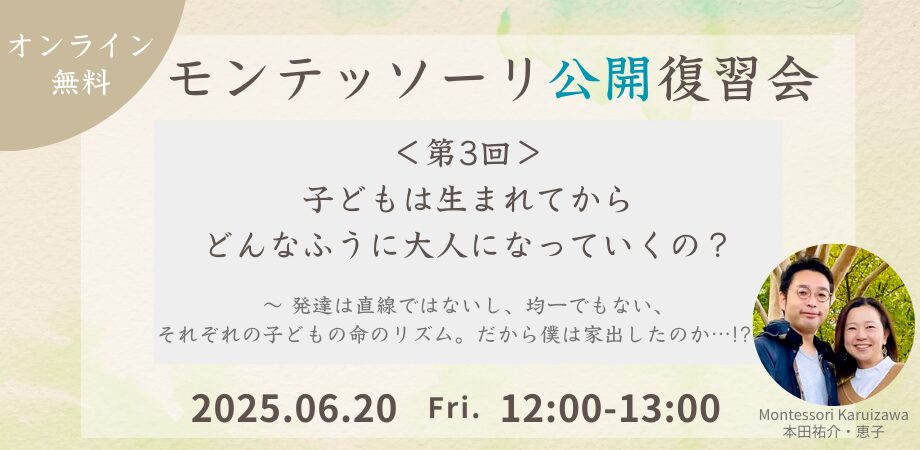
【第3回モンテッソーリ公開復習回 開催概要】
テーマ:
<子どもは生まれてからどんなふうに大人になっていくの?>
〜 発達は直線ではないし、均一でもない、それぞれの子どもの命のリズム。だから僕は家出したのか…⁉︎ 〜
──
日時:2025年6月20日(金)12:00-13:00
──
場所:オンライン開催
※お申し込みの方には別途ZoomURLをご案内いたします
──
参加費:無料
──
お申し込み方法:
Peatixよりお申し込みください

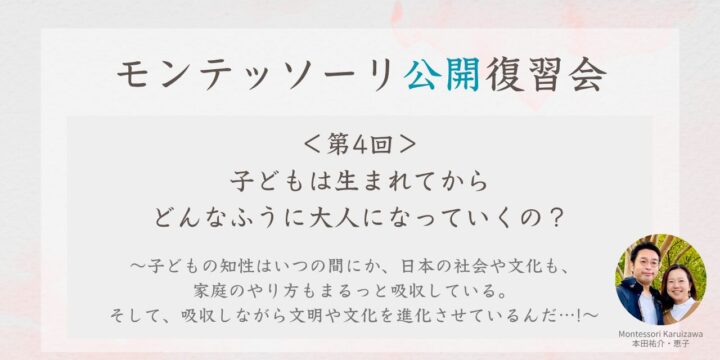
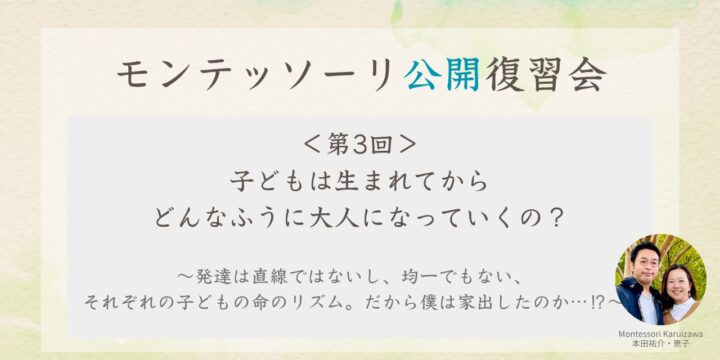

この記事へのコメントはありません。